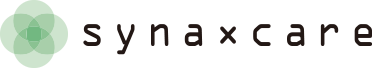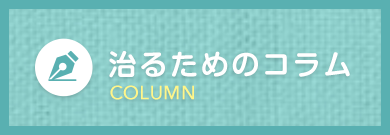総合治療院シナケア
■住所
〒465-0093
名古屋市名東区一社1-79第六名昭ビル4階4-C
GoogleMapはこちら
■TEL:052-703-5589
■受付時間:
・月~土曜日:
└午前09:00~21:00
■休診日:日曜、祝日
■アクセス
最寄駅:地下鉄東山線「一社駅」
2番出口より徒歩2分
当院は完全予約制となります。
ご来院の際は事前予約をお願いいたします。
ブログ アーカイブ
知識の備えーエコノミークラス症候群ー
\こんにちは!/
今週は、大阪を中心とした地域で大きな地震がありましたね。
ご自身やご家族はご無事だったでしょうか?
被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
こんな時、いつも「次は我が身」と思います。
東海地域でも、いつでも大きな地震が起こりうるとされていますよね。
自分自身を守るためにも、大切な人を守るためにも、
今一度、非常時グッズや避難経路など見直しをしてくださいね。
こればっかりは、起こってから考えようでは遅いのです。
シナケアでも、スタッフで改めて見直そうと思っています。
さて、こんな時だからこそのテーマ
\\エコノミークラス症候群を予防しよう//
をお伝えしようと思います(*^^*)
ご存知の方も今一度確認してください◎
\飛行機内だけじゃない、エコノミークラス症候群/
エコノミークラス症候群とは、深部静脈血栓症や肺塞栓症のことです。
名前にある通り、飛行機の移動で長時間座りっぱなしの旅行者が陥りやすいことから、
こんな名称がついていますが、最近では、震災や事故で電車等で長時間過ごすことを余儀なくされたり、
避難生活の際に車で寝泊まりする方も増えたりと、災害時に起こりうることとして、注意勧告されています。
具体的に説明すると…
食事や水分を十分にとらない状態で、車などの狭い空間に長時間座っていて足を動かさないと
血行不良が起こり血液が固まりやすくなります。その結果、血の固まり(血栓)が血管の中を流れ、
肺に詰まって肺塞栓などを誘発する恐れがあります。(厚生労働省HPより)
☆食事や水分を十分にとらない
☆長時間座って足を動かさない
この2つ、まさに!災害時に陥りやすい状況です。
\こんな方は特にお気を付けください/
高齢の方や、血管自体に障害を持つ方、がん患者の皆さん、
また、妊娠中や出産後の女性、経口ピルなどのホルモン剤を服用している女性は、
血栓(血の塊)ができやすいため特にお気を付けください。
\どんな症状が起こるの?/
どこに血栓ができるか、で症状は変わってきます。
まず足に血栓ができると、片足が腫れたり、部分的に赤くなったりなどの症状がでます。
足に痛みを伴うこともあります。
その場合、両足ではなく、片足に症状が現れる場合が多いとされています。
その足の血栓が肺に到達し、肺の血管を塞ぐようになると、
呼吸困難による息切れや胸の痛みなどの症状が現れます。
重症化すると、冷や汗がでたり、意識を失ったりするケースもありますので注意が必要です。
これらの症状が、足のみ出る場合、両方出る場合など、症状や重症度はひとそれぞれで、
症状の出るタイミングもまたそれぞれです。
じっとしている状態から脱したとしても、しばらくの間は注意して過ごしていただくのが賢明だと思います。
では最後に予防策を紹介しますね。
厚生労働省HPより引用しています。ぜひご参考にして下さい。
\エコノミークラス症候群にならないために/
・ときどき、軽い体操やストレッチ運動を行う
・十分にこまめに水分を取る
・アルコールを控える。できれば禁煙する
・ゆったりとした服装をし、ベルトをきつく締めない
・かかとの上げ下ろし運動をしたりふくらはぎを軽くもんだりする
・眠るときは足をあげる
足の指をグーパーグーパーと動かす運動もおススメです!
なんとなくでも、今日のテーマのことを頭の片隅に入れておいていただくと、
いつかの時にきっと役立つかと思います。ぜひ^^
どの災害の時にもそうですが、直後だけでなく、その後段々と疲労がたまってきて
体調を崩す方も多くいらっしゃいます。
体力や精神力、被害の大きさなど人それぞれで、無理をしなくてはいけないときも
あると思いますが、
そんな時こそひとりですべて抱え込むのではなく、助けてもらいながら
休憩しながら、一歩一歩進んでいただきたいなと思います。
微力ながらお手伝いできることがあれば、いつでもご連絡ください!
鍼灸師&不妊カウンセラー 森下
つわりのはなし
/
こんにちは!
\
みなさんいかがお過ごしですか?
田舎育ちの私(森下)は、コンクリートにやや疲れ気味。
最近土が踏みたくて仕方ありません!笑
梅雨が明けたら、キャンプに出掛ける予定です♪
さてさて、そんな個人情報はおいておいて
今週は「悪阻(つわり)」についてお話したいと思います。
妊娠希望の患者様が多くいらっしゃる当院では、気になる話題です(^_-)
/
悪阻ってなにもの?!
\
悪阻は、妊娠・出産を望む女性にとって、みんなが通る通過点。
症状のほとんどない方から、重い症状の方から様々です。
悪阻の時期も、初期で収まる方もいれば、出産まで続く方もいて、個人差があります。
悪阻の原因や個人差は何だろう?と疑問に思いますが、医学的に原因ははっきり実証されておらず、
ホルモンの関連(例えば、胎盤が完成されるまでの間に活発に分泌されるホルモンの影響など)といった説、
ストレスなどの精神的なものが原因といった説など様々あります。
悪阻は妊娠4~16週に発症し、妊婦さんの70~80%にみられます。
症状としては、起床時などの空腹時に悪心や嘔吐を訴えることが多く、
唾液の分泌過剰、食嗜好の変化、胃腸障害などの症状も認められます。
「食べづわり」「吐きづわり」「よだれづわり」なんて呼ばれることが多いですね。
/
東洋医学で紐解くと…
\
東洋医学的にみると、胎児は“陽気の塊”といわれ、それが母体に備わることによって
陰陽のバランスが陽に傾き、さらに陽に区分される上半身を中心とした症状が現れると考えられています。
(それでいうと、下半身は陰に区分されます。それで下半身に冷えを訴える方が多いんですね~)
当院の鍼灸治療では、その時々の悪阻症状をお伺いし、それにみあったアプローチをしていくことで、
悪阻症状の緩和を図っていきます。
例えば、この時期は湿気が多くジメジメした気候の影響で、
体内に湿気の溜まった「内湿」による胃腸の不調を抱えてみえる方が多くいらっしゃいますので、
内湿を流すようなツボや、胃腸を整えるツボを使っていきます。
悪阻症状も日々変化し、「昨日はこれが食べられたのに今日は食べられない」なんてこともよくあることです。
食事のバランスは二の次、自分が食べられそうなものを見つけて、とにかく旦那さんに甘える!に徹してくださいね^^
旦那さん、よろしくお願いしますね~
妊娠や出産前後に不安を抱えている方、どんなことでもご相談の問い合わせ、お待ちしております。
抱え込まず、当院にお越しくださいね^^少しでもお力になれるように、サポートさせて頂きます。
ではではまた来週♬
鍼灸師&不妊カウンセラー 森下
梅雨を快適にすごすために
/
梅雨に入りましたね~
\
こんにちは!
今週は梅雨らしく雨降りの日が続いていますね~
梅雨といえば湿気、
というわけで今週のテーマは「湿」、東洋医学のお話です。
/
この時期に気をつけたい「湿」のはなし
\
東洋医学では、病気の原因=病因のひとつに「外邪」という考えがあります。
(外邪は、外から体に侵入して病気を引き起こす原因となるもののことで、季節や気候、環境によって変わります。)
この時期の外邪は何かというと、
まさにこのジメジメした湿気が外邪となり、身体に侵入したときに様々な症状を引き起こす要因となります。
この湿気のことを「湿」もしくは「湿邪」と東洋医学では呼んでいます。
この「湿」は重く粘っこい性質があるのが特徴です。
そんな性質がある「湿」が体内に入るとどうなるか…想像してみてください。
体の中に、重―いものが入り込む感じ。粘っこいものがずっしりと滞っている感じ。。。
“(-“”-)”うーん、スッキリしないですねぇ(笑)
この時期、体が重だるいなぁ、足がむくむなぁ、頭がぼーっとするなぁ、関節が痛むなぁ…
そんな症状を感じている方は、もしかしたら「湿」が体内に入り込んで、
うまく代謝できずに滞っているのかもしれません。
また「湿」は消化機能を損なう原因にもなります。
お腹の調子がスッキリしない、下痢気味だという方はいらっしゃいませんか?
「はいはーいわたし!わたし!」という声が聞こえてきそうです(;^_^A
/
「湿」と上手につきあっていきましょう
\
そんな「湿」、どう対処したらよいのでしょう?
「湿」をため込みやすい、胃腸がよわい体質の方は、
気候に応じて食生活を調整することがおススメです。
例えば、「湿」のため込みやすい食材
△アルコール飲料や生魚、脂っぽいもの、チョコレートなど
はこの時期控えめにします。
代わりに、余分なものや水分を排出しやすくしてくれる食材
〇きゅうりやスイカ、酢、海藻類など
を多めに摂るようにします。
加えて、胃腸のを温めておくこともお忘れなく!
暑くなってきたからといって、冷たいものばかり摂っていませんか?
今からどんどん冷やしていくと、夏バテの原因にもなりますよ~!
お味噌汁や温サラダを食事の最初に摂る、というのも良いですね(^^)
食事以外で言えば、発汗することで代謝をあげて余分な「湿」を汗とともに外に出す、
ということもおススメです。
お散歩やジョギング、お風呂など、続けられる方法で♬
湿気の多い時期はこれからしばらくの間続きますから、
症状のひどくなる前に、できそうなことから生活に取り入れてみてくださいね♪
今日は文章がいつもより短めでしょ?そうでもない?
最近スイカにはまっている、
鍼灸師&不妊カウンセラーの森下でした。
女性に大切な食材のお話
/
6月に入りました
\
こんにちは!
じわりじわりと、梅雨入りが近づいてきましたね。
とはいえ、今日から週明けまでは晴れそうです♬
週末は、お出かけのご予定ありますか?
日焼け対策や、熱中症対策、そろそろ本腰いれて始めてくださいね(^o^)丿
さてさて、先週は女性ホルモンについてお話しました。
今日はその続き、「女性にとって大切な食材」についてお話しようかなと思います。
とはいえ、女性だけでなく、老若男女すべての方にとって大切な食材にフォーカスを当てていますので、ぜひ読んでくださいね♪
毎度ながら、ちょっと長文です…ごめんなさーい(/ω\)‼
/
ピックアップする食材は「脂質」と「たんぱく質」です!
\
さて、突然ですが、女性ホルモンは何から合成されているかご存知ですか?
実は、女性ホルモンは性ステロイドホルモンといって、“コレステロール”から合成されるホルモンなんです。
その点から、ひとつめの大切な栄養素として「脂質」をご提案したいと思います
とはいえ、脂質にもいろいろな種類がありますよね~。
/
おすすめの「脂質」の食材
\
で!おすすめ食材は、オリーブオイル、ごま油、亜麻仁油、大豆、大豆製品、クルミなどナッツ類、種子、アボカド、また鮭やニシンなど脂肪分が多い冷水魚、です^^
好きな食材はありそうですか?
これらには何が含まれているかというと「不飽和脂肪酸」と呼ばれる脂質です。
これらは、妊娠を希望する女性にとっても大切ですし、心臓疾患や動脈疾患の予防にもなりますので、すべての世代の方におススメの食材です。
逆に気を付けていただきたい脂質もお伝えしておきますね。
それは「トランス脂肪酸」です。
具体的には、マーガリンやショートニング、それが含まれた食品、多くのファーストフードに含まれています。
思った以上に私たちの生活の傍にこのトランス脂肪酸はあります。摂取をゼロにすることはなかなか難しいかもしれませんが、気をつけてみるだけでも随分違います。
この「トランス脂肪酸」は、そのほとんどが工場で生産されています。妊活、心臓や動脈に悪影響を及ぼすと言われています。
/
次は「たんぱく質」のちから
\
上記で紹介した「不飽和脂肪酸」の食材には、「たんぱく質」のものも多く含まれていますよね。
とても大切な栄養素のふたつめとして、この「たんぱく質」をご提案します!
肌も髪もたんぱく質からできていますし、免疫システムや体内の様々なものがこれからできています。もちろん、エネルギーとして体内で使われます。
さらに、たんぱく質はエネルギーになるだけではなく、消化吸収のよい炭水化物の代わりにタンパク質の摂取量を増やせば、高血圧や心臓病、ある種のがんなどの予防にひと役買ってくれるといわれています。
たんぱく質といえば、肉類、魚類、豆類、卵、ナッツ類など…と様々なものに含まれています。
近年、熟成肉がブームになったり赤身の肉を食べられるお店が増えて、テレビで取り上げられていることが多いですよね。私もちゃっかりそこに乗っかって、赤身のお肉が好きになりました(笑)
ただ、健康や妊活を考えた時に、動物性たんぱく質に比べて“お魚や植物性たんぱく質”をより多く摂ることをおすすめしたいのです。
偏ってお肉ばかり、お魚ばかり、お豆ばかり…になるのではなく、お肉も、お魚も、お豆も…と様々な食材からたんぱく質を摂ることで、より質の高い栄養を摂取するために
/
「できるだけ色んな食材からたんぱく質を摂る」
\
これをご提案します♬
…という風に、今日は2つの栄養素についてお話しましたが、他にも、炭水化物やビタミンなど、私たちにとってとても大切な栄養素はまだまだあります~。
それらの話はまた後ほど(^_-)
があれこれ考えすぎると、正直、毎日食事を準備する方にはツライところもありますよね(;^_^A
できるところからぼちぼちと、がとても大切です。
手を抜いても良いです、頑張らない日々があってもいいです。
美味しいと思うものを楽しく食べることが一番の栄養でもあります^^
悩む方は一緒に解決策を考えていきましょう~ご相談くださいね!
/
今日は誰とご飯を食べましたか?
\
日々の食事が、皆さんにとって楽しいものでありますように!
今日は鮭のおにぎりを食べた、
鍼灸師&不妊カウンセラーの森下でした~♬
冷え性、生理痛、更年期障害など
女性の心と身体の変化や不調をトータルにケア。
ホルモンバランスや自律神経の乱れなどからくる女性特有の不調に対して、
専門の女性治療師がお話を伺います。
生理痛・冷え性・肩こり・不妊症に
『「赤ちゃんがほしい」その想いに寄り添って』
“妊娠しやすいからだづくり” と“妊娠~出産~産後” における心と体のケアを
妊娠周期に合わせてサポートします。
女性ホルモンの基本のキ
/
こんにちは!
\
皆さんいかがお過ごしですか?
来週には梅雨入りするかも、なんて話を院内でしています。
名古屋の夏は暑いらしいですね(私、初体験でドキドキしています)…!
暑い名古屋を乗り切る策などあれば、ぜひとも教えてください!!(;´Д`)
さて、
今週は「女性ホルモン」の基本の“キ”のお話をしたいと思います。
ご存知の方も多いかもしれませんが、そんな方には復習ということでご了承ください^^
/
女性ホルモンの種類と作用
\
さて、女性にとって大切な女性ホルモンには2種類あります。
それは「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」
これらが一定の周期で分泌されることによって、「妊娠」「出産」できる体づくりをしています。
妊娠出産期でない女性の方にとっては、生理周期と深く関わってきます。
子宮や乳房名などへ様々な作用がありますが、子宮内膜にスポットを当ててお伝えすると、「エストロゲン」は、受精卵のために子宮にベッド(内膜)をつくる作用、「プロゲステロン」はそのベッドにふかふかのお布団をしいて、着床に適した状態にしてくれる作用があります。
というように、妊活中の方にとっては、受精し赤ちゃんが育つために必要なホルモンであり、
すべての女性にとって、生理周期や婦人科疾患にまつわる大切なホルモン、ということになります。
また、エストロゲンは女性生殖器への作用のほかに、身体の健康維持に重要な役割を果たしているので、バランスが崩れることで様々な症状をもたらします。
例えば、骨量の維持やコラーゲンの合成促進をしてくれる作用があるので、
エストロゲンの分泌は低下していく更年期以降、骨粗鬆症のリスクが高まると言われていたり、
生理周期によってお肌の調子が変わったり、というのはこの作用が影響しているため、という具合です。
/
分泌にまつわるあれこれ
\
そんな女性ホルモン。卵胞や黄体から“自律的に”分泌されるわけではなく、脳からの視床下部の指令で分泌されています。
ホルモン値が安定せず悩んでいる方にとってみれば、「毎月自動的に同じ量だけ分泌されると良いのに」と感じる方もいるかもしれませんが、生活環境や自然環境に適応し身体のバランスをとるために、状況に応じて脳がホルモン値など分泌量をコントロールしているんですね。人間の身体とは、うまくできています。
ストレスや生活環境等によってホルモンバランスが崩れやすかったり影響を受けやすかったりするのも、ここに原因の一つがあります。
ホルモン値が安定しない方は、一度自分の生活を振り返ってみるとよいかもしれません。
「私最近寝不足気味だったかな?」とか
「最近忙しくて、ゆっくり休んでなかったなー」とか。
どのライフステージの女性の方も、ついつい自分のからだのことは後回しにしがちですから。
自分に甘い時間も、時にはとっても大切ですよ^^
無理せず立ち止まって深呼吸しましょう♪
もちろん、男性の方も!
もっとお話ししたいところですが、ついつい長くなるので、続きは次週…
/
次回は「女性ホルモンにとって、大切な食材」について
\
お伝えしようかな~と思っています。
いつもお付き合いいただきありがとうございます♪
ついつい文章の長くなる、
鍼灸師&不妊カウンセラーの森下でした^^
冷え性、生理痛、更年期障害など
女性の心と身体の変化や不調をトータルにケア。
ホルモンバランスや自律神経の乱れなどからくる女性特有の不調に対して、
専門の女性治療師がお話を伺います。
生理痛・冷え性・肩こり・不妊症に
『「赤ちゃんがほしい」その想いに寄り添って』
“妊娠しやすいからだづくり” と“妊娠~出産~産後” における心と体のケアを
妊娠周期に合わせてサポートします。